こんにちは、はり・きゅう・マッサージ治療院feel 院長の佐野です。
「最近、なんとなく体が重い」「肩こりや肌荒れがなかなか取れない」
こうした不調の陰に潜んでいるのが、「体内の慢性炎症」という見えない問題です。
そしてこの炎症の“火種”になっているのが、実は「体脂肪」、とくに内臓脂肪です。
今回は、脂肪と炎症の医学的な関係と、その改善方法についてお伝えします。
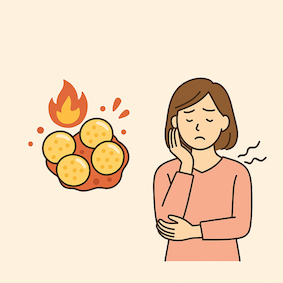
● 脂肪はただの“余分なエネルギー”ではない
脂肪、とくに内臓脂肪(腹腔内にたまる脂肪)は、単なる貯蔵庫ではなく、生理活性物質(アディポカイン)を分泌する臓器のような存在です。
そのなかでも、炎症に関わるサイトカインの分泌が問題になります。
代表的な炎症性物質:
TNF-α(腫瘍壊死因子)
IL-6(インターロイキン6)
CRP(C反応性タンパク)
これらが血中に慢性的に存在することで、関節や筋肉、内臓、さらには脳神経にも炎症が波及します。
● なぜ脂肪が炎症を引き起こすのか?
脂肪細胞の拡大によるストレス
脂肪細胞が大きくなると、内部が低酸素状態となり、細胞ストレスが発生。炎症物質を放出するようになります。
マクロファージの浸潤
肥大化した脂肪組織には、炎症性の免疫細胞(M1型マクロファージ)が集まり、TNF-αやIL-1βを放出します。
アディポカインの分泌バランスの乱れ
レプチン、アディポネクチンなどのホルモンバランスも崩れ、代謝異常や炎症を助長します。
● 医学的エビデンス
以下の研究からも、「体脂肪の増加=慢性炎症の進行」であることが裏付けられています。
Hotamisligil et al.(1993)
肥満マウスでは脂肪組織でのTNF-αの過剰発現が認められ、インスリン抵抗性にも関与していることを報告。
> Hotamisligil GS, et al. Science. 1993;259(5091):87-91.
Nicklas et al.(2004)
高齢女性を対象に、運動と食事療法による減量群では血中CRP(炎症マーカー)が有意に低下。
> Nicklas BJ, et al. Arch Intern Med. 2004;164(3):231-239.
Wellen & Hotamisligil(2005)
脂肪組織の炎症が全身性のメタボリックシンドロームの核心にあると論じる。
> Wellen KE, Hotamisligil GS. J Clin Invest. 2005;115(5):1111-1119.
● どんな症状が「炎症性体脂肪」と関係しているか?
- 慢性的な肩こり・腰痛
- 起床時の疲労感、寝ても疲れが取れない
- ニキビや肌荒れの慢性化
- 不安感、うつっぽさ
- 生理痛やPMSの悪化
- アレルギーや風邪をひきやすい
これらは、隠れ炎症(サイレントインフラメーション)」と呼ばれる状態で、病名がつくほどではないが不調が続く状態です。
● 炎症を抑えるための現実的なアプローチ
1. 筋トレ(週2〜3回)
筋肉の収縮により、IL-6などの抗炎症性ミオカインが分泌され、炎症物質を抑えます。
2. 有酸素運動(20分程度のウォーキング)
迷走神経を活性化させ、抗炎症反射が働きやすくなります。
3. 鍼灸治療
トリガーポイントを通じた局所の炎症緩和+自律神経調整により、体内の炎症トーンを下げることが期待されます。
4. 食事の見直し
糖質・トランス脂肪・加工食品の多い食生活は、内臓脂肪と炎症の両方を悪化させます。地中海食的な食習慣(魚・野菜・オリーブオイル)が推奨されています。
● まとめ
体脂肪は、ただの見た目や体重の問題ではありません。
それは、体の中に炎症をまき散らす内臓のような存在です。
『この記事の執筆者:佐野 聖(はり・きゅう・マッサージ治療院 feel 院長)』
佐野聖は1995年に鍼灸マッサージ師(国家資格)を取得。8年間にわたり整形外科クリニックに勤務し、医師との連携による臨床経験を重ねたのち、2003年に横浜にて鍼灸マッサージ治療院「feel」を開院しました。
筋筋膜性疼痛症候群(MPS)やトリガーポイントによる痛みやコリの治療を専門とし、肩こり・腰痛・坐骨神経痛・五十肩・頭痛など、多岐にわたる慢性症状の改善を得意としています。
その治療技術は、鍼灸専門誌『医道の日本』にも紹介されており、エビデンスと経験をもとに、患者様一人ひとりの痛みの本質に迫る施術を行っています。


